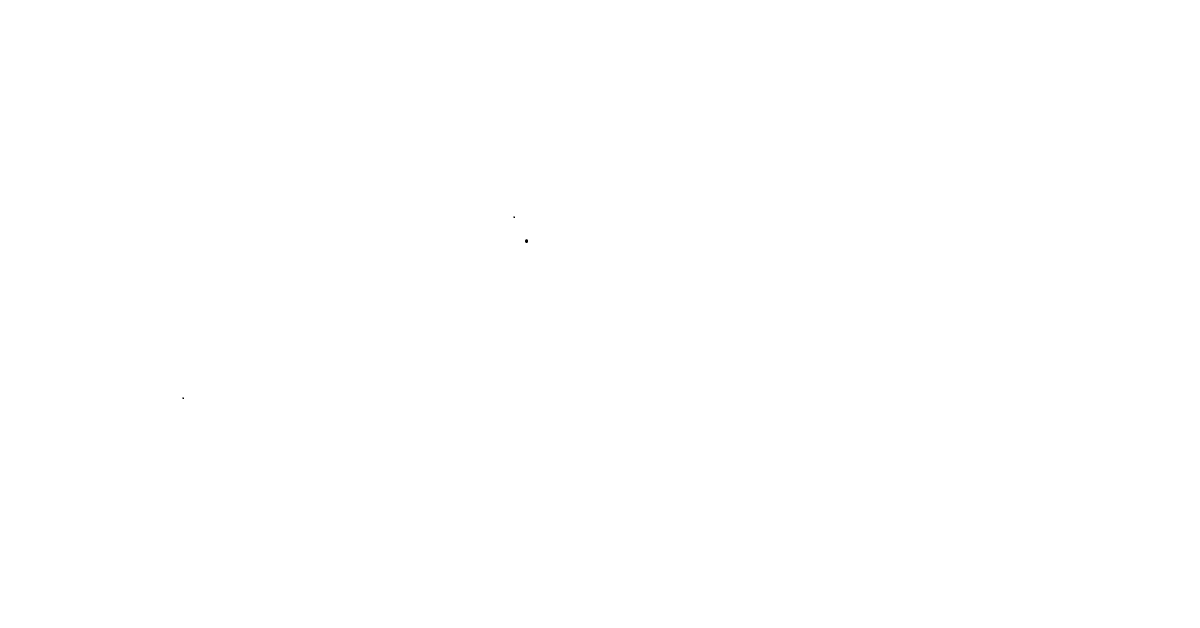急速に進化するAIやデジタル技術。新しい可能性を切り拓く一方で、その波に“取り残される人たち”が確実に存在します。
テクノロジーの恩恵を受けられる人と、そうでない人。その差は、単なるスキルの有無ではなく、社会的な構造や制度の問題でもあります。本記事では、技術の進歩に適応できず苦しむ人々の現状と、それにどう向き合えばよいかを考察します。
技術についていけない人たちが直面している現実
現代社会では、行政手続きも求人応募も、ますますデジタル化が進んでいます。しかし、スマートフォンの操作が苦手だったり、パソコンに触れた経験がない人にとって、これは生活の基盤を脅かす重大な変化です。
-
高齢者:医療・行政手続きのオンライン化に対応できず、支援が必要
-
障害者:適切なアクセシビリティ設計がないと、基本的な操作すら困難
-
教育格差のある地域出身者:情報へのアクセスが制限されており、スタートラインにすら立てない
こうした人々は、”技術についていけない”という理由だけで、社会参加の機会すら奪われる危険性があります。
誰もが生きられる社会をつくるために
1. 政策・制度による支援体制の整備
-
リスキリング支援の強化:非テック人材や失業者向けに、基礎的なITスキルからAIリテラシーまで段階的に学べる公的支援が必要
-
デジタル包摂政策:すべての市民が基本的なデジタル技術を利用できるよう、アクセス・教育・サポートを包括的に提供
-
オフライン窓口の維持:完全デジタル化の一方で、弱者を切り捨てない“複線的対応”が求められる
2. 教育の再設計と公平なアクセス
-
生涯学習型の教育制度:技術の変化に応じて何度でも学び直せる柔軟な教育環境
-
地域間格差の是正:リモート学習機会の提供やIT環境の整備により、地方や低所得世帯の子どもたちにも機会を拡大
-
実践的なデジタルリテラシー教育:SNSのリスク管理や情報の見極め方も含めた教育が不可欠
3. 非テック人材の新たな役割と評価の転換
-
人間中心の職種の再評価:介護・教育・接客など、人間らしさが求められる職業の価値を再定義する
-
アナログ的スキルの価値化:整理整頓力、手仕事、伝統技術など、AIが代替できないスキルへの注目
歴史に学ぶ:技術変化への適応と失敗の教訓
産業革命やIT革命でも、技術の波に乗れずに衰退した産業や地域は数多く存在します。そのたびに社会は痛みを伴いながらも、制度改革と教育再編で乗り越えてきました。
今回も同じです。「技術を使えるかどうか」で生きる価値が左右されるような社会にはしてはならない。
個人として今できること
-
小さな学びを始める:スマホの使い方、検索の仕方など、まずは基礎からでOK
-
地域のサポート制度を知る:市区町村のデジタル支援講座やオンラインサロンの活用
-
“教える側”として関わる:若者やテック人材が、教える活動に参加することで社会的包摂が進む
まとめ:誰もが「やり直せる社会」の設計を
テクノロジーの進化そのものが問題なのではありません。
問題なのは、変化のスピードに対して社会の制度と支援が追いついていないこと。
必要なのは、「すべての人が置いていかれず、何度でも学び直し、再挑戦できる社会」です。
それは政策・教育・文化の三位一体で進めるべき国家的課題であり、私たち一人ひとりの責任でもあります。
「誰ひとり、置き去りにしない未来」──それは技術だけではつくれない。
※関連リンク: