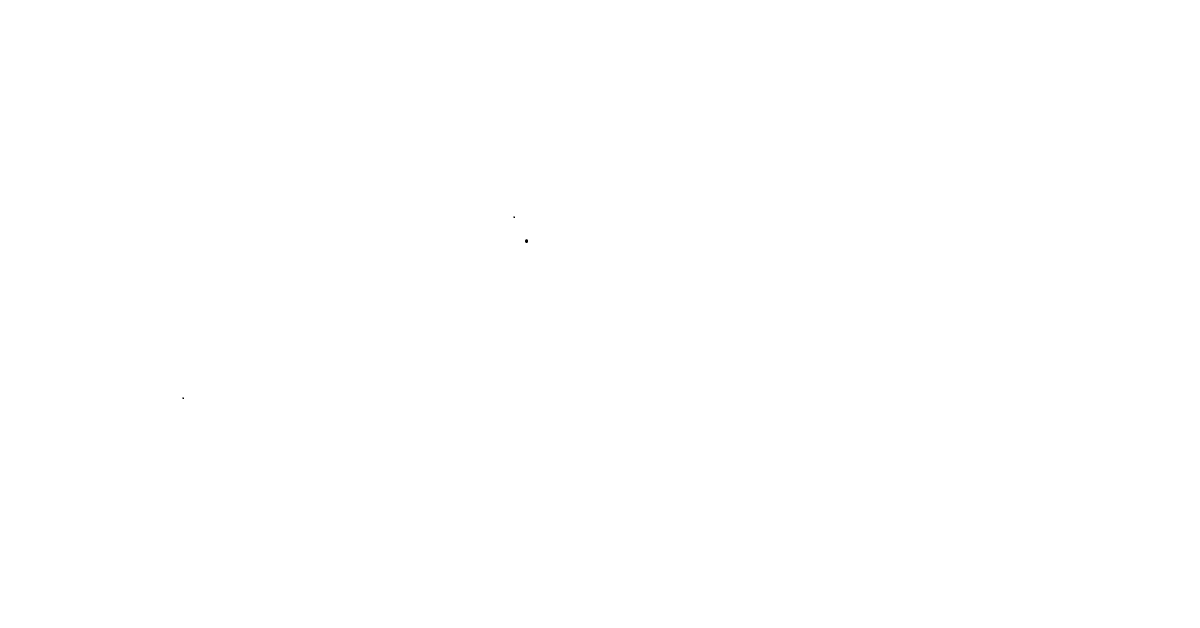現代社会では、AIやデジタル技術の急速な進化により、私たちの生活や働き方が大きく変わっています。特に障害者の方々にとっても、技術革新は大きな可能性を開く一方で、新たな課題や格差を生む側面があります。この記事では、技術進化の中で生じる障害者間の格差について考え、誰もが自分らしく生きられる社会を目指すためのポイントをやさしく解説します。
技術革新は「誰もが平等に」ではない現実
AIや義足、音声認識システムなどの技術は、身体的・視覚的なハンディキャップを乗り越える大きな力になります。例えば、プログラミングができる障害者や、中根雅文さんのように視覚障害を持ちながら高い専門性を発揮する方々は、技術によって活躍の場が広がっています。
しかし一方で、その技術を使いこなすためには一定の知識や環境が必要であり、全ての障害者が同じようにアクセスできるわけではありません。技術を利用できる人とそうでない人の間に、見えにくい「格差」が広がっているのも現実です。
「できる・できない」の壁が精神的な負担に
技術革新のスピードは速く、常に新しいツールや知識を身につける「リスキリング」が求められます。特に障害のある方にとっては、その負担が大きくなることもあります。
技術を使いこなせる人が増えるほど、「できない自分」と比較してしまい、劣等感や孤立感が強まることも少なくありません。これは決して能力の問題だけでなく、環境や支援体制の問題でもあります。
大切なのは「多様な生き方」と「包摂的な社会」
重要なのは、技術の波に乗れなかった人を排除するのではなく、多様な価値観や生き方を尊重することです。障害の有無や技術の習熟度に関わらず、誰もが尊重され、自分らしく生きられる社会をつくることが求められています。
例えば、技術サポートや教育の充実、メンタルケアの強化、コミュニティの支援などがその一歩となります。社会全体が包摂的な姿勢を持つことで、「できる・できない」による不安や孤独を減らすことが可能です。
技術はあくまで「道具」— 人間の価値は変わらない
最後に忘れてはならないのは、技術はあくまで道具であり、人間の価値そのものを決めるものではないということです。どんなにテクノロジーが発達しても、人間らしさや個々の尊厳は変わりません。
障害者の方も含め、すべての人がその人らしく輝ける社会を目指し、技術革新の恩恵を公平に享受できる環境づくりが今後ますます重要になるでしょう。